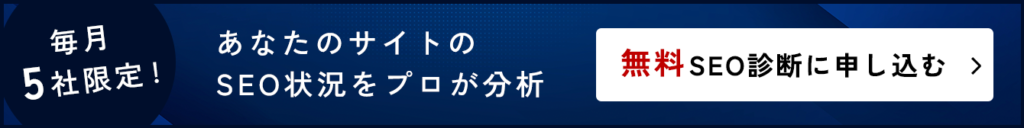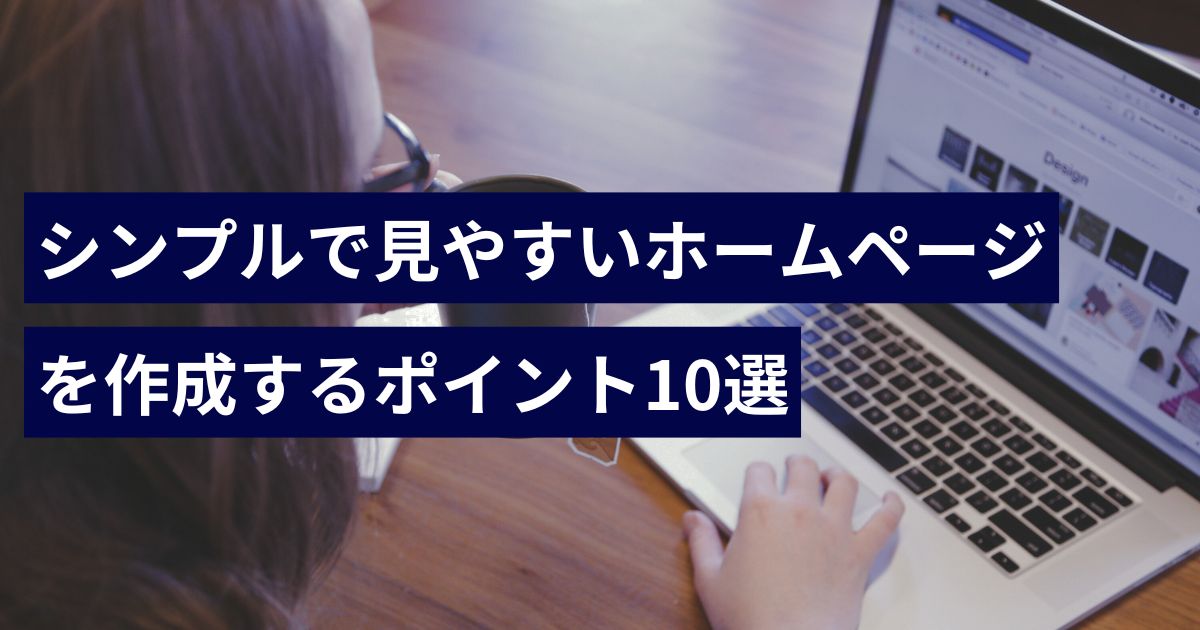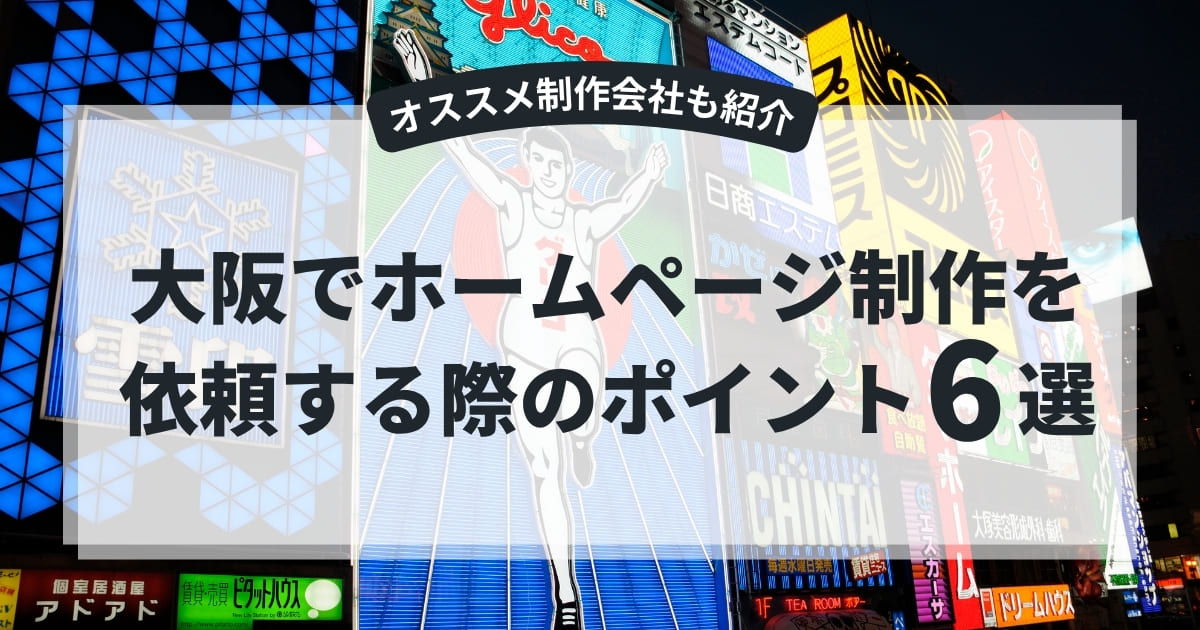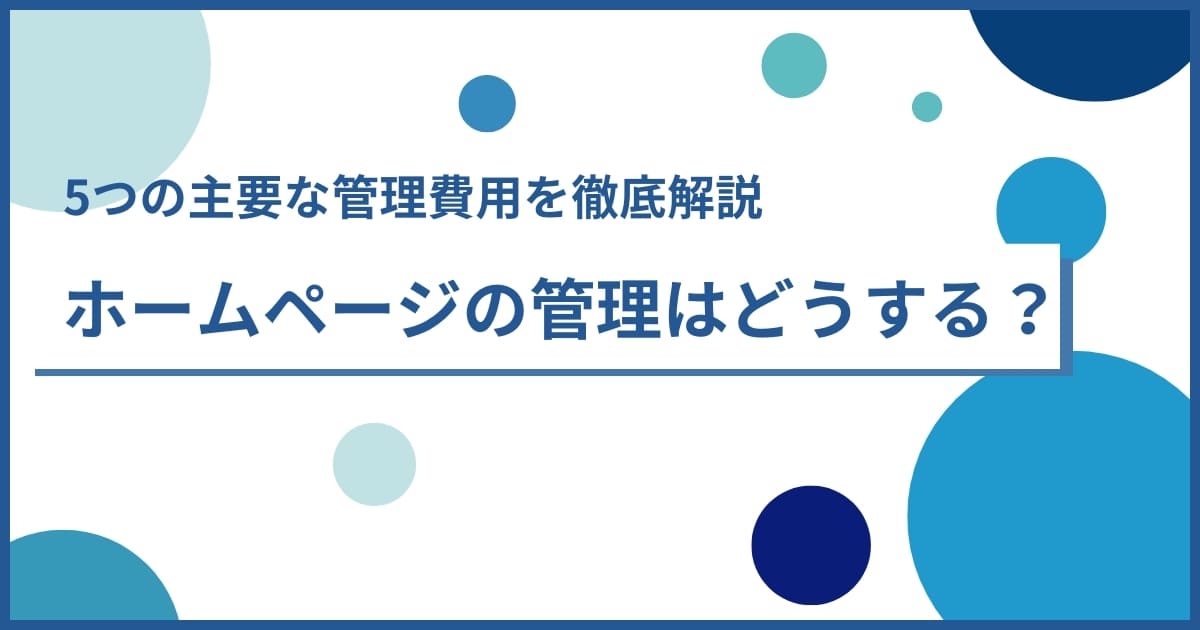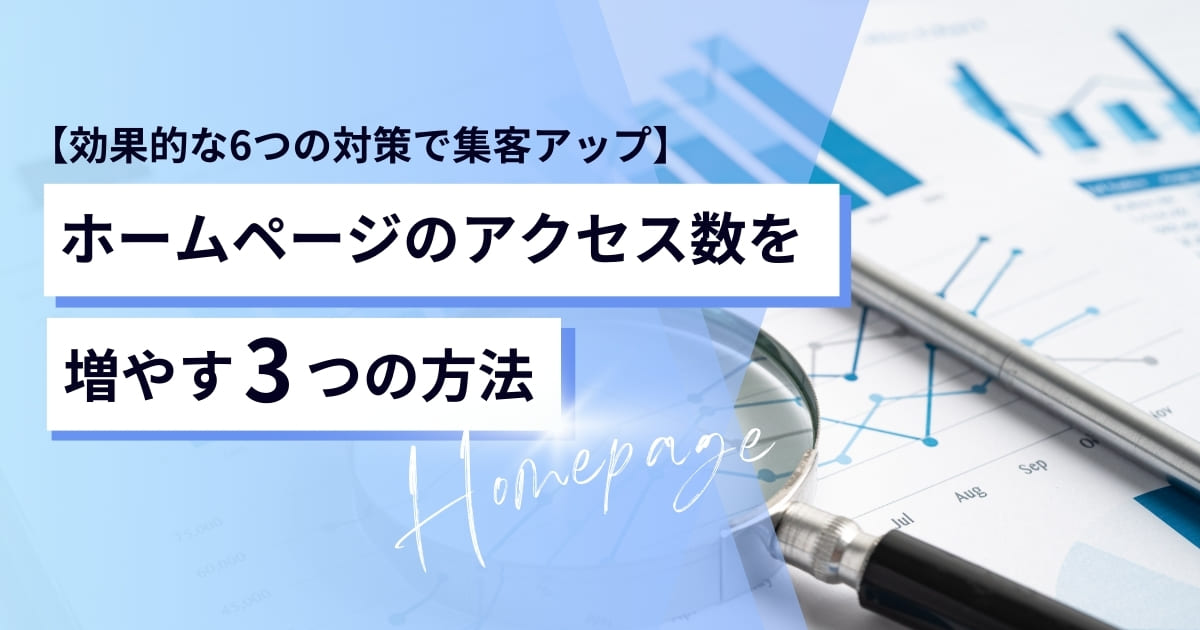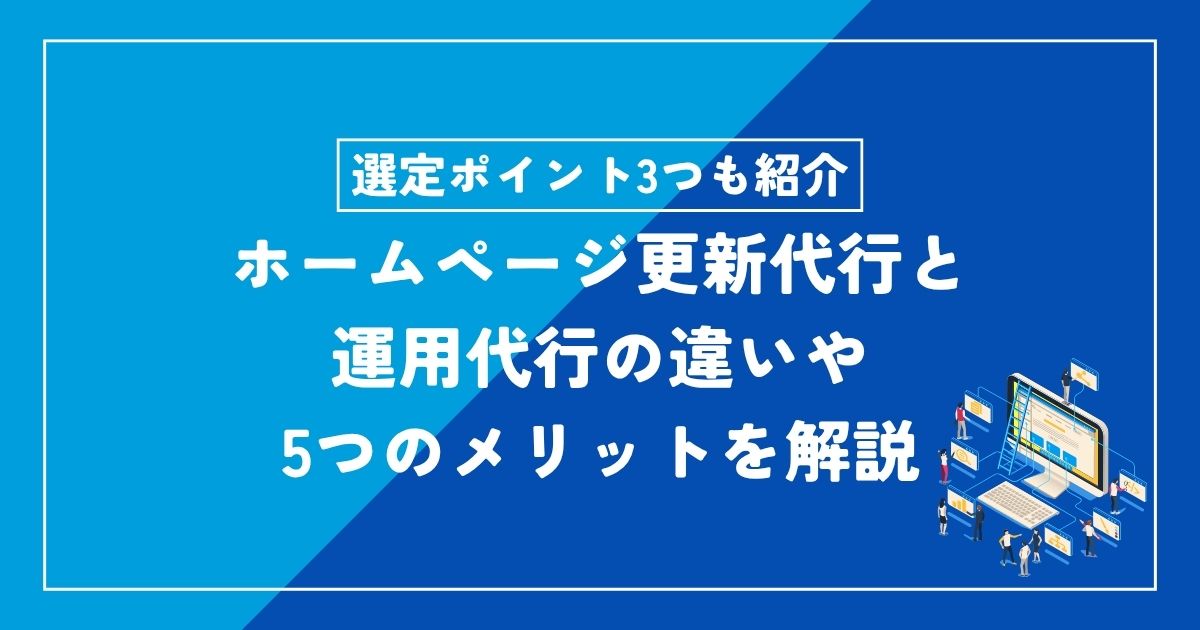見やすいホームページを作成するにはポイントがあり、しっかり理解して作成すればユーザーや検索結果にも良い影響を与えます。
今回は、おしゃれかつシンプルで見やすいホームページを作成するポイントを10個紹介します。
自社のホームページを作成する際の参考にしてください。
なお、筆者はSEOに関して以下の実績を持っており、SEOの悩みやお困りごとを解決できます。

SEO会社の代表
・WEBサイト制作実績100件以上
・SEO対策後、半年でECサイトの売上190万円→580万円と3倍以上にした経験あり
・WEBサイト制作も行っているため、サイトの内部からSEOの評価をアップ
また、毎月5社限定で無料であなたのサイトのSEO分析を行っています。気になる方は下記バナーをクリックしてください。
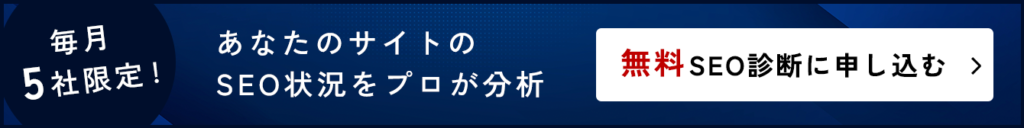
目次
見やすいホームページとは
見やすいホームページとは、ユーザーが迷うことなく目的の情報にたどり着けて直感的に操作できるサイトです。
今回は見やすいホームページを作成するために、事前に持ってほしい考え方を3つ紹介します。
①ユーザーを意識した設計
②デザインの見極め
③ホームページの目的を明確にする
紹介した考え方を持ったうえで、自社にとって魅力的な見やすいホームページを作成してください。
考え方①:ユーザーを意識したレイアウト・設計
1つ目の考え方は、ユーザーを意識したレイアウト・設計にすることです。
ユーザーの立場に立って「何を求めているか」「どのような行動を取るか」を徹底的に考えてください。
たとえば、企業サイトなら「会社概要」「サービス内容」「お問い合わせ」といった基本情報への導線を分かりやすく配置します。
2〜3クリック以内で目的のページにアクセスできるように設計すると、ユーザーからの評価も向上しやすくなります。
また、検索機能やサイトマップの設置・パンくずリストの表示など、ユーザーが迷わない仕組みを整えてください。
ユーザーにとって使いやすいホームページは、Googleからの評価も上がりやすく検索上位表示させやすくなります。
考え方②デザインの見極め
2つ目の考え方は、ホームページのデザインを見極めることです。
トップページを開いた瞬間に「このサイトで何ができるのか」「どんな情報が得られるのか」が明確に伝わるデザインが理想的です。
また、背景色と文字色のコントラストなど色の使い方も重要になり、ブランドカラーを効果的に活用しているかも確認しましょう。
さらに、余白の使い方やフォントの統一感・画像の品質と配置バランスも考慮した設計を意識してください。
見た目の美しさだけでなく機能性と使いやすさを意識したホームページを作成すれば、ユーザーも利便性を感じやすいです。
考え方③:ホームページの目的を明確にする
3つ目の考え方は、ホームページの目的を明確にすることです。
目的が曖昧なホームページは、ユーザーにとって分かりにくく離脱率の高いサイトになります。
たとえば、「商品やサービスの販売」「会社の信頼性向上のための情報提供」など、明確な目標を設定します。
目的に応じてホームページ全体の構成やデザインを統一し、ユーザーが迷わずに行動を取れるよう導線を設計します。
さらに、ターゲットとなるユーザー像を明確にすることも重要です。
年齢層や職業・興味関心などを具体的に想定して、ユーザーにとって価値のある情報を優先的に配置します。
目的やターゲットを明確にすればコンテンツの取捨選択がしやすくなり、ユーザーにとって見やすく使いやすいホームページを作成できます。
おしゃれ・シンプルで見やすいホームページを作成する10のポイント
実際に見やすいホームページを作成する際のポイントを10個紹介します。
①デザインの4大原則
②視線誘導の3パターン
③フォントの選び方と可読性
④配色とコントラストの最適化
⑤画像やCTAボタンの活用
⑥効果的なライティング
⑦導線設計
⑧レスポンシブデザイン
⑨情報の選別
⑩仮説と検証を繰り返す
紹介した全ての要素を実施して欲しいですが、まずは優先順位を決めてできる範囲で始めてください。
ポイント①:デザインの4大原則
1つ目のポイントは、デザインの4大原則を理解することです。
デザインの4大原則とは「近接」「整列」「反復」「対比」であり、原則を押さえたホームページは格段に見やすくなります。
- 近接:関連性の高い要素を近くに、関連性の低い要素を遠くに配置する原則
- 整列:縦横のラインを揃えて、情報を見やすくする原則
- 反復:同じ役割を持つ要素には同じデザインを繰り返し使用する原則
- 対比:要素間の強弱をつける原則
4つの原則を組み合わせれば、ユーザーにとって見やすいホームページが完成するため、意識してみてください。
ポイント②:視線誘導の3パターン
2つ目のポイントは、視線誘導の3つのパターンを理解することです。
人間の目の動きには一定のパターンがあり、3つのパターンを意識したレイアウトにすればユーザーの視線を誘導しやすくなります。
・Z型パターン
視線は「左上→右上→左下→右下」へと移動するため、目の動きに合わせて重要な情報を配置します。
チラシや雑誌・ファーストビューにも使用されており、初めて訪問するユーザーにも内容が伝わりやすいです。
・F型パターン
左上から右へ視線が移動した後に左から右へと水平に動き、最後に左側を縦に流し読みするパターンです。
そのため、見出しや重要な情報は左側や最初に配置すると効果的なホームページが作成できます。
・N型パターン
視線が「右上→右下→左上→左下」に向かって移動するパターンで、縦書きのレイアウトに使われます。
旅館や呉服店など、日本らしさを演出したいコンテンツの場合に最適なパターンです。
3つのパターンを理解しつつ適切に使い分ければ、ユーザーにとって見やすく行動しやすいホームページを作成できます。
ポイント③:フォントの選び方と可読性
3つ目のポイントは、フォントの選び方と可読性です。
フォントサイズや行間・フォントの種類を統一すれば、画面上での視認性が向上し見やすいホームページになります。
たとえば、日本語のホームページでは游ゴシックやヒラギノ角ゴ・メイリオなどのゴシック体を基本とすると見やすいです。
さらに、ひらがなやカタカナ・漢字の割合を意識して作成すれば、読みやすくなり最後まで閲覧してもらえる可能性も高まります。
ポイント④:配色とコントラストの最適化
4つ目のポイントは、配色とコントラストの最適化です。
適切な配色は、ユーザーの目の疲労を軽減して情報を効率的に伝える役割を果たすため、意識して選択する必要があります。
たとえば、文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上に設定すると、ユーザーの目に優しいホームページが作成できます。
また、企業のブランドカラーを活用しつつ、メインやサブ・アクセントカラーの3色を基本とした配色設計がおすすめです。
ホームページで色を使いすぎると視覚的に混乱を招くため、以下の割合で配色して見やすくしましょう。
- 基調となるベースカラー:70%
- ベースカラーを引き立てるサブカラー:25%
- 強調色であるアクセントカラー:5%
ポイント⑤:画像やCTAボタンの活用
5つ目のポイントは、画像やボタンの活用です。
画像は高品質でサイズが適切なものを選び、ページの読み込み速度を考慮した形式で保存するようにしましょう。
商品やサービスの魅力を伝える画像は、テキストよりも直感的に情報を伝えられてユーザーの関心を引きつけられます。
さらに、お問い合わせや資料請求・購入などの行動を促すCTAボタンは、目立つ色とサイズで配置してください。
ボタンの文言は具体的で分かりやすく、「クリックして詳細を見る」や「今すぐ申し込む」など、ユーザーが次に取るべき行動を明確に示しましょう。
さらに、画像とボタンの配置バランスも重要であるため、自然にユーザーの目線が重要な情報にたどり着けるようにデザインしてください。
ポイント⑥:効果的なライティング
6つ目のポイントは、効果的なライティングです。
ホームページの文章は、ユーザーにとって読みやすく理解しやすい内容にする必要があります。
たとえば、一文は短く簡潔にまとめ、専門用語を使う場合は必ず説明を加えるようにしましょう。
ユーザーの立場に立って難しい表現は避け、日常的に使われる言葉を選択して作成すると親しみやすさが生まれます。
また、改行を効果的に使って視覚的な余白を作れば、ユーザーも余裕を持ってホームページを閲覧できます。
さらに、具体的な数字や事例を盛り込むと、説得力が増して読み手の信頼を得やすいです。
ポイント⑦:ユーザーを意識した導線設計
7つ目のポイントは、ユーザーを意識した導線設計です。
導線設計とは、ユーザーがホームページ内で迷わずに目的を達成できるように適切な道筋を作ることです。
ユーザーの行動パターンを理解し、トップページから商品購入やお問い合わせまでの流れを明確にする必要があります。
たとえば、グローバルナビゲーションを画面上部に配置し、主要なページへのリンクを常に表示するとユーザーは移動しやすくなります。
また、パンくずリストを設置して「ユーザーが現在どのページにいるか」を把握しやすくするのもおすすめです。
ユーザーが「どの場所にいるか」を把握できれば、たとえ迷った場合でもユーザー自身で修正して必要な情報にたどり着けます。
ポイント⑧:レスポンシブデザイン対応
8つ目のポイントは、レスポンシブデザイン対応です。
レスポンシブデザインとはパソコンやタブレット・スマートフォンなど、どのデバイスでも最適な表示ができるように自動調整される仕組みです。
たとえば、画面サイズに応じて文字サイズや画像・レイアウトが自動的に変化すると、どのデバイスでも見やすくなります。
なお、Googleもモバイルファーストインデックスを採用しているため、レスポンシブルデザインに対応していないサイトは検索順位が下がる可能性があります。
ユーザビリティと検索エンジン対策の両方の観点からも、レスポンシブデザインは見やすいホームページを作成するためには必要です。
ポイント⑨:掲載する情報の選別
9つ目のポイントは、ホームページに掲載する情報を選別することです。
ユーザーが求める情報を素早く見つけられるよう、掲載する内容を厳選すれば目的の情報をみつけやすくなります。
たとえば、企業サイトであれば会社概要や事業内容・お問い合わせなどの基本的な情報を優先します。
情報の優先順位を決める際は、「80:20の法則(パレートの法則)」を活用すると効果的です。
「80:20の法則(パレートの法則)」は、ユーザーの8割が求める2割の重要情報をトップページに配置し、残りの詳細情報はサブページで掲載する法則です。
また、情報量が多い場合はカテゴリーごとに分類し階層構造を作ると、ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けます。
ポイント⑩:仮説と検証を繰り返す
最後のポイントは、作成したホームページの仮説と検証を繰り返すことです。
見やすいホームページを作成するためには、常に仮説を立てて検証を行い改善を繰り返す必要があります。
ユーザーの行動パターンや求める情報を仮説として設定し、それに基づいてレイアウトやコンテンツの配置を決定します。
実際にホームページ公開後は、Googleアナリティクスやヒートマップツールを活用して、ユーザーの実際の行動データを収集しましょう。
離脱率が高いページやクリックされやすいボタンなどを分析し、仮説の正確性を確認してください。
データを基に問題点を特定したら改善案を実装してA/Bテストを実施し、ホームページのクオリティを向上させます。
見やすいホームページを作成して企業の売上や集客を向上させよう
今回は見やすいホームページを作成するためのポイントをお伝えしました。
ホームページは1度作成して終わりではなく、ユーザーにとっての見やすさを考えながら改善を繰り返す必要があります。
紹介したポイントを1つでも意識して自社ホームページを作成して、売上や集客を向上させてください。
REEING株式会社では、SEOコンサルティングを行なっており、毎月5社限定で無料でサイトを分析し、SEOレポートの共有まで行っています。
プロだから気付けるあなたのサイトの問題点を隅々まで洗い出します。
毎月すぐ定員に達してしまうため、今すぐ下記からご連絡ください。